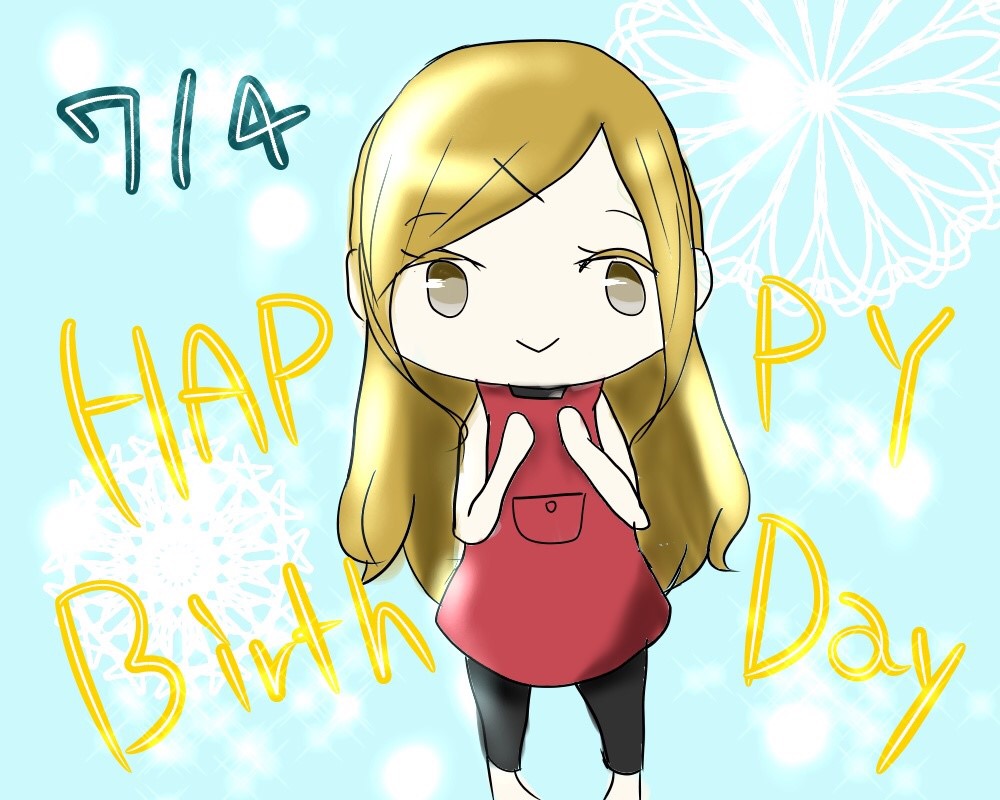白っぽい石を積み上げて造られた小さな家は、外観と内部の作りがまるで違っていた。
薄い灰色とクリーム色のストライプに囲まれた壁。玄関を入るとすぐに重そうなテーブルが置いてあり、薪がくべられた暖炉が、ぱちぱちと歌いながら外との気温差を作り出していた。
それはとても心地よく、暖かな空間──。
暖炉の前、オーク色の床に直に座り込み手を火にかざしながら、少女はほうっと息を吐いた。
彼女の身体を覆うものが薄くてぺらぺらのショールから、ふわふわの厚手の毛布に変わっていた。暖められた空気とその毛布とに包まれて、とても気持ち良かった。
数分前、死と隣り合わせだったことを忘れそうだ。
「どうですか。少しは暖まりましたか」
かちゃかちゃと陶器の音とともに、優しい声がした。
少女は慌てて立ち上がり、声の方を振り返った。
「あ、いえいえ」
青年は彼女の後ろに鎮座する黒い長方形のテーブルに、持っていた茶器セットをそっと置きながら言った。
「そのままで。まだそこで暖まっていてください」
「あ…はい、ありがとうござい……ます」
青年の笑顔に顔を赤くしながら、少女は俯いて呟くようにささやく様に答えた。
こんなに美しい人を、少女は見たことがなかった。
いや、記憶を無くしているから正確なところは分からないのだが、きっと彼以上に綺麗な人間には以前に会ったことなどないと思うのだ。
一度でも見たら、他のすべてを忘れても、彼を忘れられはしない。
そんな青年だったから。
言われた通り、暖炉の前に座り直し、また手をかざす。
ゆらめく炎は変わらず暖かかった。
「それにしても」
優雅な手つきでお茶を淹れながら、青年は言葉を紡ぐ。
「本当に寒かったでしょう。さぁ、とりあえずお茶を」
座り込む少女のもとへ、淹れたばかりのお茶を運ぶ。
「ありがとう……」
受け取ろうとした少女の頬を見て、青年は微笑んだ。
「ああ、少しは暖まってきたようですね。頬に色が」
少女の頬は更に色を増した。
受け取ったティーカップから湯気が立ち昇る。恥ずかしさを隠すように黙ってカップに口をつけた。
コクン。
伏せていた瞳がぱっと見開かれた。
「おいし…」
それは例えようのない、不思議な味だった。
くるくるとカップの中を満たしていたのは、七色に変わるお茶。
「お気に召しましたか」
「はいっ」
勢いよく答えた少女に、青年はとても嬉しそうに微笑んだ。
部屋は暖かく、得も言われぬ味と香りの美味しいお茶に、それに、素性の分からぬ自分を優しく招き入れてくれた穏やかで美しい住人。
少女は自分の胸に、こみ上げてくるものを感じた。
「……大丈夫、ですよ」
青年は少女の隣りに座り、その小さな肩をぽんぽんと優しく叩いた。
「すぐ、思い出します」
少女の顔が泣きそうに歪んだ。
『……さん……さん』
丘から見渡す草原に、爽やかな風が吹き抜ける。
足元には春に咲くという黄色と白の花。
誰。
よく見えない。
少女ははっとした。
今のは。
白昼夢のような、映像がほんの少し見えた気がした。
「お茶を飲んで。まずはゆっくり暖まりましょう。こんな薄着で長い時間外にいたのですから」
何だろう、気のせいかな。
青年の言葉に頷いた。
長い、時間。
手にしたお茶をゆっくりと口に運んだ。
風に揺れる緑、黄色、白。
空は青に少しだけ灰色を混ぜた春特有の色をしていた。
『おかあさん、はる、あった!』
風に揺れる小さな花に、座り込み、鼻スレスレまで顔を近づけた。
すーん、とその香りを力いっぱい吸い込んだ。うん、甘酸っぱい。
『はるー』
顔をあげて笑顔で叫んだ。
『見てあの子。嬉しそう』
『ああ、それもとびっきりにな』
大好きな二人がこちらを見て笑っている。
こちら、私の方を……女の子を……。
女の子……。
「女の子は、私?」
「え?」
頭の中に浮かんだ映像に、ふと思い出す。
そうだ、あの小さな女の子は……あれは私だ。
あの人達も見覚えがある。
大好きな、大好きな。
「大丈夫ですか」
青年のコバルトブルーの両の瞳が、心配そうに揺れていた。
「あの、私、いま」
彼を見上げ口ごもり、また目を伏せた。
そんな少女に青年は優しく問いかけた。
「もしかして、なにか思い出したのですか」
ぱっと顔をあげた。
「はい!あの、小さい頃を…多分小さい頃のことだと思うんですが」
青年はまたにっこりと笑った。
「それは良かった」
青年は少女の前に新しく皿を差し出した。カップとお揃いらしい角皿に人型の焼き菓子が並んでいる。
「このお菓子もお気に召すといいのですが」
「かわいい‥‥」
両手をバンザイした形の焼き菓子をそっと手に取り、口に運ぶ。サクッとした食感に顔がほころんだ。
「美味しい、美味しいです」
素直な感想だった。
と、水分を持っていかれすぎたのか、うまく呑み込めず咳き込んでしまった。
「ごほっ、ごほごほっ」
「あぁ、いけない、詰まりましたね。早くお茶を」
話をしていた間に適度に冷めたお茶を勧められ、少女は慌てて飲み干した。
「大丈夫ですか」
背中をさすりながら、青年は心配そうに声をかけた。
少女は首を縦にして大丈夫だと伝えたが、口の中のすべてを飲み干した瞬間、目眩に襲われた。
視界が真っ白になっていく。
そのまま、白い夢の中に引きずり込まれるように、気を失った。