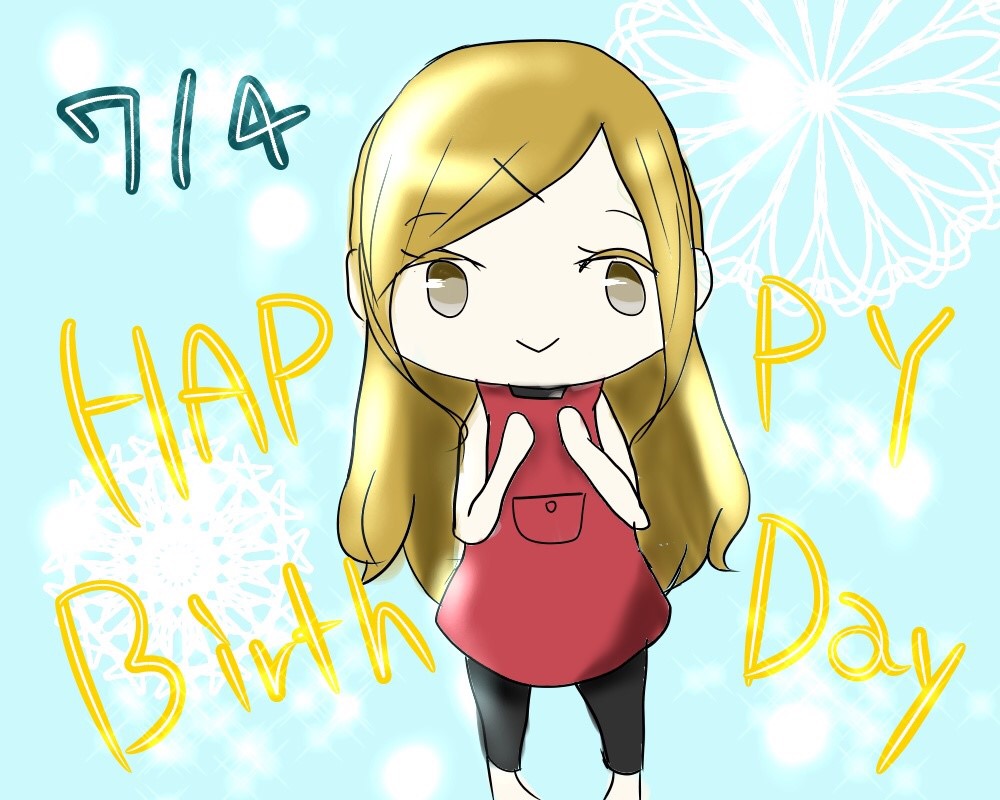さらさらと流れる水。
冷たくて冷たくて……目が覚める。
たまに見るこの夢は、年を重ねる毎にぼやけていく。あと少し経てば、見なくなるのかもしれない。なにかの記憶のような、そうでないような。意味もなさげなのに何故こうも長い間夢にでるのか、そこは不思議だったが。
「イーちゃん!」
ばたばたと足音が聞こえてきたかと思うと、勢いよく扉が開いた。
「イーちゃんごめん、お父さん、また忘れちゃった」
眉を八の字にさせて入ってきた母親が、申し訳なさそうに言った。今日は特にくるくる巻き毛の母親は、何かの小動物に見えて仕方がない。
「いい、お母さん可愛いから行ってくる」
サッと、ベッドから降りて身支度を整える。
「やだ、可愛いって」
まんざらでもなさそうにふにゃ~と口元を緩めながら、自分の横を通り過ぎようとする娘に手にしていた包みを差し出す。
まあ、いつものことだ。
「ごめんね~。あ、お弁当くるくるしないのよ?」
「うん」
行ってきます、と言い残して家を出た。
お父さんはよく忘れ物をする。お弁当なんてその最たるものだ。お弁当をくるくる回しながら歩く。
あ。
「また回しちゃった」
ぺろっと舌を出した。
「イーリアちゃん、こんにちは。今日はお休みかい?」
市場近くまで来ると、馴染みの果物屋のおばさんが声をかけてきた。イーリアの持つ包みにチラッと視線を向けると分かったような顔になる。
「またかい?」
「そう、またなの」
果物屋のおばさんにまでこんなこと言われてるなんて、お父さんったら。
自然に笑みがこぼれる。
おばさんにバイバイと手を振って、両脇にびっしりと店が並ぶ通りをまっすぐに歩いていく。イーリアの後ろ姿を見ながら、おばさんは一人呟いた。
「ますます綺麗になっていくわね~。あのプラチナブロンドの長い髪はどっちにも似てないようだけど」
彼女が通り過ぎていくと、皆が振り返っていく。
村一番の器量良し。それが彼女、イーリアだった。
まって。
これはなに?
微かに開いた瞳に掠れながら映る暖炉の火。それは一瞬。
また白に飲み込まれる。
『おかあさん、はる! あった!』
一面の花畑。低い目線、小さな手。
見上げてそこにいるのは、いるのは、、お母さん。
綺麗なプラチナブロンドの髪を結んで片方に垂らした、背の高い……。隣で笑う男の人は……お父さん……。
二人が遠ざかる。
まって、ねぇまって。
「じゃあ……さっきの人は誰」
言いながら目を開く。
そこは知らぬ、けれど暖かいベッドの上だった。少女は混乱した。
さっき見たのは夢、これも夢なのか。
起き上がって周りを見るも、何も見覚えがない。ただ先ほどと違うのは、触感があること。滑りの良い毛布を握りしめながら必死に考えた。
と、そこへあの青年が扉を開いて入ってきた。
少女はほっとした。彼は知っていたから。
「目が覚めたんですか。具合は」
心配そうに近寄ってくると、彼は少女の額にそっと手を触れた。
少女は思わず身を竦める。
くすりと笑いながら青年はその手を引いた。
「熱はないようですね」
こくり、と頷くだけで少女は精一杯だった。彼は美しすぎる。間近で見ると息ができない。青年の手が触れた額を隠すように、前髪を引っ張った。
「それで、どうですか。少しは何か思い出せましたか」
その言葉に、少女ははっとした。
彼の美しさに戸惑っている場合ではなかった。今はあの夢、その話をするべきなのだ。少女は毛布を握りしめ、先ほどの夢を話した。
「母親と思える人が二人ですか……」
少女が話し終えた後、青年は誰に問うでもなくぼそりと呟いた。訊かれたとしても分からないから頷いておいた。
「ただ、おかしいと思うところが」
「え?」
「私、多分私の年が違ってて……三歳か四歳かと、もう働いているくらいの歳で。おかしいですよね。私まだ子供なのに」
過去と、未来でも見たのか。
自分の小さな手を見つめながら、少女は唇を噛んだ。
何もかも分からないことに腹が立つ。
「うーん、そうですね……」
青年が手にしていた暖かな衣服を少女の前に置きながら言った。
「とりあえず、これに着替えて、ご飯食べませんか」
少女はちょっとだけ目を丸くして、青年と渡された服を交互に見、短く返事をした。ご飯と聞いて、お腹の虫が喜んで鳴きそうになっていたので、ここは素直に。
「聞こえたら恥ずかしい……」
青年が部屋を出た後の、少女の一人言。
渡された着替えは少女にぴったりとはいえなかった。わりと大きめのワンピースで、少女は袖をかなり捲り上げねばならなかった。裾は床にすれすれ。もう少し長ければ、床掃除ができそうだ。
だが、今まで着ていたものよりとても暖かい素材で出来ていたので、寒いと思うことはなくなった。
着替えが終わり、ベッドを降りて部屋を出た。
そこは最初に暖まらせてもらった暖炉のある部屋だった。今もその暖炉はパチパチと音をたてている。黒のテーブルには美味しそうな料理が並んでいた。
「あ、そこ、座ってください」
奥から青年がひょこっと顔を出し、少女を見てぴたりと止まる。
「あぁ」
そうして破顔する。
「その服、よく似合いますね」
少女の顔が真っ赤になったのは仕方がない。
──つづく。