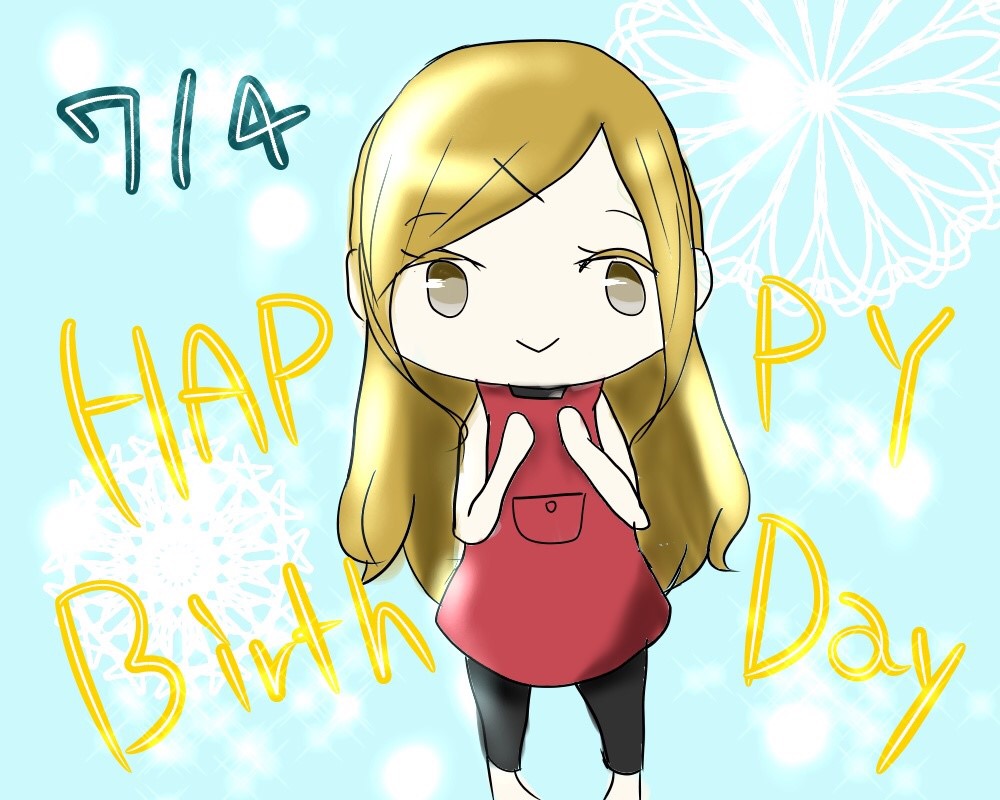こんにちは、鈴音 駿です。
この小説は別の長編小説の中に出てくる、ある国のお話です。
本編は読まずとも単独で読めます。(ちなみにまだ本編は書いていません笑)
戦いのシーンがありますので、少し暴力性・流血がでるかと思います。
この点にお気をつけてお読みくださればと思います。
見上げる天は薄暗く、地は水を孕み、その上を踏む圧力に悲鳴の代わりの濁音をあげる。
ガジュッ、ガジュッ。
空と地の間は冷えた空気で満たされ、時折吹く風には白いものが混じっていた。
───なぜ。
少女は羽織っていたショールをマントのように被りなおした。
霜が降り、小雪の舞うこんな日には到底相応しくない丈の短い薄い生地の服、むき出しの素足の先を少し覆っただけの靴。
吐く息も白く、まさしく季節とは真逆の服装で、なぜ。
なぜ私は。
ともすれば風に引き剥がされそうになるショールをぎゅっと握りしめ、少女は何度考えたであろうことを、また考えた。
それは突然だった。
ふと、見上げた空。
少女の記憶はそこから始まる。遡れるのはほんの一時。
「こ、ここ、、え? え?」
きょろきょろと周りを見回す。右に左に、ぐるっと一周。二度見回してもここが何処か全く分からなかった。
葉のない、変色した木々。草も花もここにはない。
少女の立つそこは、冬に入った森だった。
不可思議なのは、少女は眠っていたわけではない。瞬きは、したかもしれない。
したかもしれないが、瞬きした瞬間に、己のことも、この場所にどうやって来たのかも忘れてしまったというのか?
びゅうっと、突風が吹いた。冷たくて、氷の刃のようで、触れられた頬はもすでに真っ赤だ。震える指でショールを握り、顔を覆う。
「さ…さむい……」
冷たい身体を片手で抱く。触れたところをさすりながら、少女は記憶を辿ろうとした。そして、愕然とした。自らの記憶が、ほんの小さじ程度もないことに。
これがほんの少し前のこと──。
「わた、わたし、」
寒くて、唇もうまく動かせなくなりつつあった。ひゅっと冷たい空気を吸い込んで、少女は咳き込んだ。寒い。先ほどよりも更に寒さが増している気がした。
とにかく、歩かなきゃ。
げほげほと咳をしたあと、口に添えた手で唇を拭いながらそう思った。
何もない森の中、黙って立ち尽くしているだけなのは死を意味している。
そうして少女は道なりに歩き出した。
前に進んでいるのか、それとも戻っているのかはどうにも分からなかったが。
手も足も自分のものでなくなった頃、木々の合間の空に昇るひと筋の線が目に入った。
もしかして。
少女は逸る気持ちに小さな胸を震わせた。
もしかして。
鉛のような足を必死に引きずって進んだ。
やがてひと筋の線は煙突から出る煙となり、そうしてそれは小さな石造りの家の煙突からの煙だと分かった。
家! 家だ!!
はぁはぁと乱れた呼吸に声もでなかったが、心の中に歓喜の言葉が浮かんだ。
ここからは早かった。どこにそんな体力が残っていたのかと自らも疑うほどに鉛の足も気にならず、一心に石造りの家へと歩いていく。
早く、早く。
心が急くのに身体が呼応していくのが分かるような、少女の走り方だった。
やがてたどり着き、扉の前に立つと、今持てる力全てをかけて叩いた。
「……す……すみ」
かすれて出にくくなった声が、乾いた冷たい空気の中を泳ぐ。
聞こえないのだろうか。
が、ざっと見渡しても呼び鈴のようなものはない。上部が半円の形をした可愛らしい木の扉。取っ手を握り、ガチャガチャと揺らしてみる。開かない。
自分を撫でる風の冷たさに、恐怖が込み上げる。
既に日が暮れる。これから凍てついた冬の夜が始まるのだ。こんな真夏の服装で外にいれば、確実に生が終わる。なにを覚えていなくとも、それだけは理解していた。
最悪窓を割ってでも中に入らなきゃ……。
物騒なことを考え出した少女の何度目かの呼び出しに、かちゃり、とようやく扉は応えた。
──つづく。